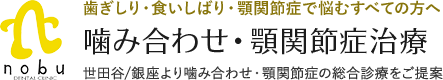歯ぎしり食いしばりはストレスを解消することで治りますか?
投稿日:2025年11月5日
カテゴリ:歯ぎしり・食いしばり
「気がつくと歯を食いしばっている」「朝起きると顎周囲の筋肉が疲れている」——そんな経験をしたことはありませんか?
歯や顎の痛み、肩こり、頭痛の原因として知られる歯ぎしり食いしばり。
多くの人が「ストレスをなくせば食いしばりは治るのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。
今回は、歯ぎしり食いしばりとストレスの関係、そしてストレスだけで解決できるのかどうかについて、歯科の視点から解説します。
歯ぎしり食いしばりとストレスの関係
ストレスが歯ぎしり食いしばりを引き起こすというのは、確かに正しい側面があります。
人は緊張や不安を感じたとき、気づかぬうちに拳を握りしめたり肩をすくめたりするように、無意識に体に力を入れてしまう傾向があります。
これは、人類が狩猟を行っていた時代の名残で、狩るか狩られるかという極限のストレス下で戦うにしても逃げるにしても即座に動けるように体に力を入れるようになるわけです。
同じような仕組みで、咬筋(こうきん)や側頭筋といった噛むときに使う筋肉が過度に働き、上下の歯を強く噛み合わせる歯ぎしり食いしばりが起こります。
つまり、心理的ストレスが増えると、
→ 筋肉の緊張が高まる
→ 無意識に歯を噛み締める
という流れが生まれ、食いしばりの頻度が高くなるのです。
では、そういったストレスを解消すれば治るのか?
結論から言えば、ストレスの解消で軽減はすると考えられますが、それだけで歯ぎしり食いしばりが完全になくなるとは限りません。
歯ぎしり食いしばりは先述のような自身を取り巻く環境からの外因的なストレスだけでなく、以下のような身体的・構造的要因、いわば内因的なストレスが複雑に関係しているためです。
1. 噛み合わせや顎の位置の不調和
歯の高さや、虫歯治療でセットした被せ物や詰め物のバランス、矯正後の噛み合わせの変化などにより、顎が最も安定する位置(安静位)がわずかでもずれてしまうと、筋肉が緊張しやすくなります。
結果として、顎関節や咀嚼筋に微妙なストレスがかかり、体が無意識に噛み合わせを補正しようとして歯ぎしり食いしばりが生じることがあります。
2. 呼吸の状態(口呼吸・いびきなど)
鼻づまりや口呼吸の癖があったり、頭顔面の発育の関係上呼吸環境が良好でない人は、下顎が後方へ引かれ、それとともに舌自体も喉の奥に押し込まれていることで気道が狭くなっていることが多いです。それを防ぐために体が無意識に軌道を確保しようと下顎を前方へ押し出そうとして歯ぎしり食いしばりが生じます。そういった呼吸環境の不良も見逃せない要因になります。
3. 姿勢の崩れ
長時間にわたる不自然な姿勢を保持するデスクワークや、呼吸環境の悪化(気道狭窄)による代償的な反応である「ストレートネック」や前傾姿勢も、歯ぎしり食いしばりを助長します。
頭が前に出た姿勢では下顎の位置がずれるのでそれを補正しようと顎関節周囲の筋肉が常に緊張する状態になってしまうのです。
このように、ストレスだけが唯一の原因ではないのです。
歯ぎしり食いしばりを改善するためにできること
1. 心理的ストレスのケア
ストレスが強い時期に歯ぎしり食いしばりが増加すること自体はほぼ避けられません。そのため、リラックスの習慣(副交感神経を優位にさせる習慣)を意識的に取り入れましょう。
深呼吸、ストレッチ、入浴、軽い運動、質の良い睡眠の確保など、日常の中で体の緊張を緩める時間をつくることが大切です。
また、寝る前のブルーライト(スマートフォンやPC)やカフェイン摂取をコントロールするなど、「自律神経を整える」生活も効果的です。
2. 歯や顎への物理的な負担を減らす
夜間の歯ぎしり食いしばりがある場合には、歯科でナイトガード(マウスピース)を作製するのが簡便で一般的です。
上下の歯が必要以上に接触すると、下顎の位置を保持しようとして反射的に顎を動かす筋肉が緊張してしまいます。それが原因で歯ぎしり食いしばりが増悪する負のスパイラルに陥る可能性があります。マウスピースを用いて歯を保護したり、噛み合わせを持ち上げて奥歯の干渉を減らすことで、筋肉や顎関節への負担を軽減し、痛みや摩耗を防ぐことができます。
3. 歯と歯の接触に関しての意識付け
日中、「上下の歯は離れているのが正常」という意識を持つことも重要です。というのもリラックスしているときは、上下の歯はわずかに離れ、唇が軽く閉じているのが自然な状態で、上下の歯が接触するのは食事と喋るときのみとされているからです。「歯を離す・舌を上あごにつける・鼻での呼吸」という3点を意識するだけでも、顎周囲の緊張は和らぎます。
4. 噛み合わせや呼吸環境の診査診断・評価
あらゆるストレス対策を実践しても改善しない場合は、歯や顎の構造的問題が隠れていることもあります。
専門的な診査や資料採得を行い、それによりなされる診断の結果、噛み合わせ・顎関節・呼吸の通り方などを包括的に評価し、顎の位置の矯正や補綴治療、必要に応じて外科的アプローチも選択肢に加えて治療の提案を行います。
まとめ
歯ぎしり食いしばりは確かにストレスと密接に関係しています。そのため、ストレス解消による歯ぎしり食いしばりの軽減は見込めると思います。
しかし、そういった世間一般的に言われていいる「ストレス」を完全になくしても、噛み合わせや姿勢、呼吸といった身体的要因にルーツがある問題が残っていれば症状は残存・再発することもあります。
歯ぎしり食いしばりが長く続く場合は、早めに専門医でチェックを受けてみましょう。
心身のバランスを整えることが、健やかな顎と笑顔を守る第一歩となります。
■ 他の記事を読む■