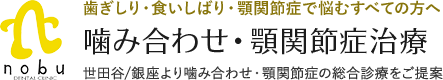顎関節症の症状に吐き気などはありますか?
投稿日:2025年3月14日
カテゴリ:歯ぎしり・食いしばり 顎関節症
顎関節症は、顎の関節や周囲の筋肉に異常が生じることで、痛みや開口障害、関節音などの症状を引き起こす疾患です。よくある質問として顎関節症の症状として「吐き気」はあるのでしょうか?というものがありますのでお答えします。
結論から言うと、吐き気は顎関節症の主症状ではありません。しかし、顎関節症が間接的な要因となり、吐き気が生じるケースはあるようです。本記事では、そのメカニズムと対策・治療法についてお話したいと思います。
吐き気は顎関節症の主症状ではない?
まず、顎関節症の主な症状ですが、一般的に挙げられるのは以下のようなものです。
-
・顎関節の痛み(顎関節周囲が押すと痛かったり、咀嚼時に痛みがでたりする)
-
・口を開け閉めするときの顎関節から音が鳴る(カクカク、ミシミシといった音=関節雑音)
-
・口が開けにくくなる(開口障害)
-
・噛み合わせの違和感
-
・頭痛や首・肩のこりや痛み
これらの症状は多くの患者に見られますが、「吐き気」が直接的な症状として報告されることはほとんどありません。ただし主症状に起因する副次的な要因によって吐き気が引き起こされることがあります。
顎関節症が原因で吐き気が生じるメカニズム
顎関節症に関連して吐き気が生じるメカニズムには、以下のようなものがあります。
自律神経の乱れ
顎関節症の患者は、長期間にわたる痛みやストレスにより交感神経が優位になりやすい傾向があります。その影響で自律神経のバランスが崩れやすくなります。その結果、消化器系の働きが乱れ、吐き気を感じることがあります。
耳の異常(内耳への影響)
顎関節は耳のすぐ近くにあるため、顎関節への長期的な負荷が内耳に影響を及ぼすことがあります。内耳の機能が乱れると、平衡感覚が崩れるので、めまいや吐き気を引き起こすことがあります。
心理的要因
顎関節症による慢性的な痛みや不快感が心理的に悪影響を及ぼし、胃腸の働きを悪化させることで吐き気を誘発することがあります。
顎関節症に関連する吐き気がある場合の対策と治療法
顎関節症の治療を行う
吐き気の原因が顎関節症に関連している場合、まずは顎関節症の治療を行うことが重要です。治療方法には以下のようなものがあります。
-
・スプリント療法(マウスピース): 噛み合う顎の位置を誘導することで顎関節の負担を軽減する。
-
・理学療法(ストレッチ・マッサージ): 顎や首の筋肉をほぐし、血流を改善し、姿勢の見直しを行う。
-
・生活習慣の見直し: 硬いものを摂取する頻度をコントロールしたり、知らないうちに噛み締めているようであればそれを解くように意識付けをしたりして、顎への負担や顎の筋肉の緊張を緩和させていく。
自律神経を整える
自律神経の乱れによる吐き気を防ぐために、以下のような方法を取り入れると効果的です。
- ・適度な運動: 血流を改善し、自律神経のバランスを整える。
-
・十分な睡眠: 睡眠不足や質の低い睡眠は自律神経の乱れを悪化させるため、しっかり睡眠時間を確保し、かつ質の高い睡眠を得られるようにする。
ストレス管理
ストレスによる自律神経の不調を軽減するために、以下の方法を試してみましょう。
- ・カウンセリングを受ける: 心理的なストレスが強い場合は、専門家に相談する。
-
・リラクゼーション法(ヨガ、瞑想): 精神的な安定を得るために有効といわれるアクティビティを実践する。
内耳の検診・治療
もしめまいを伴う場合は、耳鼻科を受診し、内耳に問題がないか確認することをお勧めします。顎関節症の治療だけでなく、めまいや平衡感覚を改善する治療を受けることも検討するようにしましょう。
まとめ
顎関節症の主症状として吐き気が直接現れることはほとんどありませんが、副次的な要因として生じる可能性はあります。原因に対して適切に対処することで、吐き気を軽減・解消することが可能です。まずは顎関節症の治療を行い、必要に応じて生活習慣の見直しやストレス管理を行うことが大切です。
もちろん生じている吐き気が顎関節症のみが原因ではなく、他の原因や疾患も関与している可能性も考えられることもあるため、自己判断するのではなく歯科医や内科、耳鼻科などの医師に相談・診査診断を経て総合的に、場合によっては他科連携での治療を行うことをおすすめします。
■ 他の記事を読む■