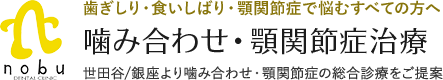なぜストレスが原因で歯ぎしり食いしばりが起こるのでしょうか?
投稿日:2025年8月17日
カテゴリ:歯ぎしり・食いしばり
「ストレスが原因で歯ぎしりや食いしばりが起こる」と耳にすることはあっても、その仕組みを正確に理解している人は少ないかもしれません。
実は、歯ぎしりや食いしばりは単なる“クセ”ではなく、心身のバランスが崩れた結果として現れる体のサインです。そしてそのストレスには、大きく分けて「外からのストレス(心理・環境的な要因)」と「内からのストレス(身体の内部的な不調和)」の2種類があります。
※それぞれを今回の記事では仮に「外的ストレス」と「内的ストレス」と呼ぶようにします。
この記事では、これら2つのストレスがどのように歯ぎしり食いしばりと関係しているのか、そのメカニズムをわかりやすく解説します。
外からのストレスが歯ぎしり・食いしばりを引き起こす理由
1. 精神的なストレス(心理的不安など)が筋肉の過緊張を引き起こす
人間は緊張や不安を感じると、無意識に体に力が入ります。怒りや焦り、不安、プレッシャーといった心理的ストレスを抱えているとき、無意識のうちに顎の筋肉を強く締めたり、上下の歯を噛み締めたりするようになります。この「無意識の噛みしめ」は、デスクワーク中や運転中、または寝ている間に起こることが多く、慢性化すると筋肉や顎関節にダメージを与え、歯ぎしりや食いしばりとして定着してしまいます。
2. 自律神経の乱れ
ストレスは交感神経(活動モード)を優位にさせ、自律神経のバランスを乱します。この交感神経優位の状態では、筋肉が常に緊張しやすくなり、夜間の歯ぎしりや日中の食いしばりが起こりやすくなります。また、交感神経が活性化すると、睡眠の質も悪化し、レム睡眠(浅い眠り)の時間が長くなります。このタイミングで歯ぎしりが発生しやすくなることもわかっています。
歯ぎしり食いしばりが生じる原因として最もメジャーなのが上記2つでしょう。それらは、大昔に人類が狩猟を行っていた時代背景が関係しています。その頃は獲物や敵を眼の前にしたとき、「戦う」のか「逃げる」のか、相手の出方を伺うことは日常茶飯事でした。「Fight or Flight 反応」と言われる、交感神経優位となり、どちらにでもすぐさま転じることが出来るように身構える極限状態が由来とされています。このとき、下顎を安定させることは姿勢を安定させることに繋がり、全身の筋肉を適度に緊張させることはすぐさま動きに転ずる事ができます。そういった過去の名残として、交感神経が優位となるとき、下顎を安定させるために歯と歯を噛み合わせて食いしばるわけです。
内からのストレス(身体の不調和)が原因になることも
歯ぎしり食いしばりの原因は、先述のようなものだけではありません。身体に潜む不調和や機能的な問題もストレスになりえます。それらは脳に“危険信号”として伝わり、それを無意識に補おうとする働きの一環として歯ぎしり食いしばりが生じるケースもあります。
1. 顎の位置のズレ・噛み合わせのアンバランス
顎の関節や噛み合わせにわずかなズレがあると、脳は「正常な咀嚼ができていない」と判断します。これにより、無意識にそのズレを噛みやすい位置に調整しようと動かします。しかし、歯や顎の骨の形や構造上、その噛みやすい位置に動かせないとき、筋肉に過緊張が生じ、歯ぎしり食いしばりで無理やりその位置に動かそうとするのです。
これは一種の身体が自ら歪みを修正しようとする防御反応のようなものであり、抑止できません。顎のズレがある限り、いくらメンタル面を整えても歯ぎしりが完全には治まらないのは、こういったことが関与しているから、と言えるでしょう。
2. 不良な呼吸環境
気道や鼻の奥(咽頭部)が狭いなどして呼吸環境が悪いとき、意外にもそれらは歯ぎしり食いしばりとも密接に関連していることがあります。
ここでいう「呼吸環境が悪い」とは通常の鼻での呼吸がしにくいこととした上でお話を進めていきます。
呼吸環境が悪いと、その代わりに口呼吸をするようになります。意識している、していないに関わらず、そして気道を広げるために猫背気味に顔を前に出すようになります。すると下顎に付着している筋肉群が下顎を後ろに引き下げようとする力が加わります。この状態が慢性的に続くと、下顎が引き下げられ、奥歯が強く当たる環境ができてしまいます。これを咬頭干渉といい、本来当たらなくて良いタイミングで歯と歯が接してしまう現象をいいます。結果として干渉が起こるたびに顎を動かす筋肉が緊張し(=力が入り)、歯ぎしり食いしばりを併発します。
また、口呼吸は通常の鼻呼吸より酸素の換気量が多くなります。血中酸素濃度が高まると勝手に交感神経が優位になってしまいます。それにより歯ぎしり食いしばりが出現するだけでなく睡眠の質が低下したり、イライラしやすくなったりと精神面にも影響が現れます。なお、小児における注意欠陥多動性障害(ADHD)は、これらとの関連が示唆されています。
さらに、慢性的な口呼吸は舌の位置や顎の成長に影響を与え、噛み合わせや顎の位置の不調和を助長し、結果として内因性のストレスとなります。
歯ぎしり食いしばりへの対策:外からも内からもアプローチを
歯ぎしりや食いしばりの対策には、「ストレスマネジメント」と「身体の環境整備」の両輪で取り組むことが大切です。
【外的ストレスへの対策】
-
・心理的ストレスの原因を把握し、コントロール出来る環境を整えたりする(仕事、職場、人間関係など)
-
・カウンセリングやマインドフルネスなどのメンタルケア
-
・眠る前にリラックスする習慣をつける(適切な副交感神経が優位となるような入浴・入眠アプローチなど)
【内的ストレスへの対策】
-
・噛み合わせや顎関節の検査に基づく調整や治療(歯科での咬合診断)
-
・鼻呼吸を促すトレーニング、耳鼻科の受診による呼吸改善
-
・マウスピース(スリープスプリント)で就寝中の呼吸環境悪化を軽減
-
・顎の位置や姿勢改善を目的とした専門的なカイロプラクティック
まとめ:歯ぎしり食いしばりは“こころ”と“からだ”からの救援信号
歯ぎしり食いしばりは、外からのストレスだけでなく、身体の機能的な不調和=内的ストレスの影響でも起こります。
つまり、それは単に「遺伝」や「クセ」などで片付けられるものではなく、心身両方からの“異常のサイン”ととらえるべきものなのです。
原因を明確にしないまま放置すると、顎関節症、歯や詰め物被せ物などの破折・破損といった口や顎のトラブルだけでなく頭痛や肩こりなどの全身のトラブルに及んだりします。また、精神的安定にも影響が懸念されます。
大切なのは、自分のストレスの「出どころ」がどこにあるのかを専門的な診断をうけて知ることと、外からも内からも可能な限りこういった問題点を最小化していくことです。
■ 他の記事を読む■