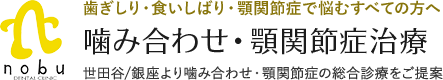歯ぎしり食いしばりが全身に与える影響ってどんなの?
投稿日:2025年7月14日
カテゴリ:歯ぎしり・食いしばり
「歯ぎしり食いしばり」と聞くと、歯がすり減ったり顎が痛くなったりと、口の中だけのトラブルだと思われがちですが、実は全身の健康にも大きな悪影響を及ぼすというのをご存知でしょうか?
慢性的な歯ぎしり食いしばりは、自覚がなくても日常生活の質に影響を及ぼしているリスクがあります。この記事では、歯ぎしり食いしばりが身体全体に及ぼす悪影響を具体的に列挙し、その原因・メカニズム・解決策まで詳しく解説します。
歯ぎしり・食いしばりが全身に与える悪影響とそのメカニズム
1. 顎関節症(TMD)の原因となり顎の運動に制限が出る
【影響内容】
顎の痛み、開口障害(口が開きにくい)、顎のカクカク音などが発生して、食事や発語に影響が出る。
【メカニズム】
強い歯ぎしり食いしばりが続くと、顎関節に大きな負担がかかり、関節のズレや炎症、変形を引き起こします。慢性的に続くと顎関節症へと進行し、口が開きにくくなったり運動障害が生じるようになります。
2. 頭痛・肩こり・首こりの誘発される
【影響内容】
歯ぎしり食いしばりにより顎周囲の筋肉が緊張し、胸鎖乳突筋を中心とした首周囲の筋肉が連鎖的に緊張するので、慢性的な頭痛や、肩・首のだるさ、重さを感じる。
【メカニズム】
歯ぎしり食いしばりは、咬筋(噛む筋肉)や側頭筋(こめかみ部分)を過剰に緊張させます。この緊張が頭・首・肩の筋肉に波及し、血流が悪化します。それによる筋肉の酸欠状態が続くことで、慢性的な痛みやコリを引き起こします。
3. 睡眠障害・疲労感の蓄積
【影響内容】
寝ても疲れが取れず昼間に強い眠気や倦怠感を感じやすくなります。
【メカニズム】
夜間に歯ぎしり食いしばりが頻発するということは、REM睡眠時間が多いということでもあります。REM睡眠はどちらかというと浅い眠りになりますので、深い睡眠が妨げられ、脳も筋肉も十分に休息できない状態に陥るため、慢性的な疲労や集中力低下を招きます。
4. 歯の破折・詰め物や被せ物の脱離・知覚過敏の原因
【影響内容】
歯が欠ける、詰め物が外れる、冷たいものがしみる。
【メカニズム】
歯ぎしり食いしばり時の咬合力は、通常咀嚼時の数倍~10倍にもなり、歯のエナメル質がすり減り、微細な亀裂(マイクロクラック)が入ることがあります。その影響で知覚過敏や歯の破折、補綴物の脱落が生じやすくなります。また、そのヒビにむし歯菌が侵入してむし歯になるケースも多いです。
5. 顔貌のゆがみ・筋肥大(エラの張り)
【影響内容】
顔が非対称に見える、エラが張って顔が大きく見える。
【メカニズム】
どんなひとでも顔が左右対称であることはない、という前提でお話するのですが、歯ぎしり食いしばりにより片側の咬筋ばかりが過度に発達したり、顎関節症や歯並びの影響で下顎骨の位置がズレたりすることで、顔の非対称やエラの張りを引き起こします。美容的にも気になる大きな影響です。
6. 消化不良・胃腸不調の間接的原因に
【影響内容】
胃もたれ、食欲不振、便秘や下痢など。
【メカニズム】
歯ぎしり食いしばりは慢性的な交感神経優位(いわゆる緊張状態)を招きます。その状態が続くと、副交感神経優位のときに働く胃腸の動きが悪くなりますので、消化不良を招きやすくなり、胃腸トラブルを引き起こすこともあります。
歯ぎしり食いしばりの主な原因
歯ぎしり食いしばりが生じるそもそもの原因は、大まかにわけると以下のような原因が挙げられます。
-
・ストレスなどの心理的要因
→ 日中の緊張やイライラが、夜間の歯ぎしり食いしばりを誘発。 -
・噛み合わせの不良
→ 上下の歯の必要以上の接触があると、無意識の歯ぎしり食いしばりを助長。 -
・職業性・習慣性(クセ)
→ パソコン作業や運転中の無意識の食いしばり。 -
・睡眠時無呼吸症候群との関連
→ 無呼吸時の覚醒反応と連動して歯ぎしり食いしばりが生じることがある。
歯ぎしり・食いしばりの解決・治療方法
1. マウスピース(ナイトガード)の使用
最も一般的で簡易な対策です。保険診療。就寝時に装着することで、歯や顎関節への負荷を軽減できます。歯科医院で個人に合わせたマウスピースを作ることが推奨されます。
2. 咬み合わせの調整
噛み合わせ異常が原因の場合は、歯の高さを微調整したり、矯正治療が有効です。もちろん、ちゃんとした顎の診査診断が欠かせません。
3. ボツリヌストキシン注射
筋の過剰な働きを一時的に弱める治療法で、歯ぎしり食いしばりによる歯や顎への過度な負担を軽減できます。数カ月ごとのメンテナンスが必要です。
4. ストレス管理
心理的要因が強い場合は、カウンセリングやストレス解消法(運動、リラクゼーション、深呼吸)も重要です。就寝前などの入眠の環境を整えることも有効です。
5. 睡眠環境の改善
質の良い睡眠を確保することで、夜間の歯ぎしりを減らすことが期待できます。寝る前のスマホやカフェインの摂取を控え、睡眠リズムを整えることも有効です。
まとめ
歯ぎしり食いしばりは、単に歯をすり減らすだけでなく、顎関節症、頭痛、肩こり、睡眠障害、胃腸トラブル、顔の歪みといった、深刻な悪影響をもたらします。
しかし、原因を理解し、マウスピースの装着、咬み合わせ治療、ストレス管理など適切な対策を講じれば、これらのリスクは大幅に軽減できます。
「なんとなく最近、疲れやすい」「朝起きると顎がだるい」と感じている方は、一度歯科医院で相談することをおすすめします。
早期に対処することで、全身の健康を守ることにつながります。
■ 他の記事を読む■