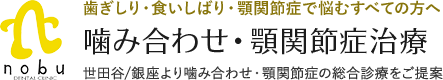あくびをしたら顎や耳の前あたりが痛くなった…これって顎関節症?
投稿日:2025年1月6日
カテゴリ:顎関節症
日常的に起こり得る「あくびをした後に顎が痛くなった」という症状。これは、一時的に生じる顎関節症である可能性があります。
たかがあくびくらいで…というお考えもあるかもしれません。
しかし、突然の顎周囲に強い痛みが出たり、顎が動かしにくくなったりした場合は早めの対策が重要です。
今回は、こういった場合の原因やメカニズム、対策方法や治療法について詳しく解説します。
あくびによる顎の痛みの原因
以下のようなことがあくびによって引き起こされると顎の痛みやトラブルを引き起こしたりします:
-
過剰な口の開閉
あくびの際には大きく口を開けます。この動作が過度に、かつ急激に行われると、顎関節の軟骨や靭帯に過剰な負荷がかかることがあります。それによって関節内部に炎症や損傷が生じる可能性があります。奥歯が欠損したりして噛み合わせが不安定な場合、顎関節の構造に負担が生じる状態が常に存在します。その場合、大きく口を開けた際に関節円板(顎関節内のクッションの役割を果たす部分)がずれて正常な顎の運動を妨げることがあります。これが痛みや可動域制限の原因になります。 - 噛み合わせが不安定な場合の関節円板への過負荷
奥歯が欠損したりして噛み合わせが不安定な場合、顎関節の構造に負担が生じる状態が常に存在します。その場合、大きく口を開けた際に関節円板(顎関節内のクッションの役割を果たす部分)がずれて正常な顎の運動を妨げることがあります。これが痛みや可動域制限の原因になります。 -
肉の緊張や疲労
顎周囲の筋肉が疲労していると、過剰に口を開ける動作が筋肉の過緊張を引き起こし、痛みを感じる場合があります。 -
既存の顎関節症状の悪化
もともと軽度の顎関節症状があった場合、あくびのような強い動作で悪化することがあります。
メカニズム:なぜ痛みが生じるのか
顎関節は硬組織(骨)と軟組織(筋肉や軟骨など)によって非常に複雑な構造をしており、下記の要因が絡み合うことで痛みが発生します:
- 軟骨の炎症
関節内部で摩擦が増えると、軟骨が炎症を起こし痛みを感じます。 - 関節円板の異常
円板がずれることでスムーズな動きが妨げられ、痛みが生じます。 - 周囲筋肉の過緊張
動きの不安定さを補うために筋肉が過剰に働き、緊張や炎症が引き起こされます。
あくびで顎にトラブルが起きたときの対策と応急処置
あくびの後に顎が痛くなった場合、以下の対策を試みると症状の緩和につながることがあります:
-
顎を安静に保つ
痛みが続く間は顎を動かすのを控えて安静に努めましょう。硬い食べ物やガムなどは当然避け、しばらく柔らかい顎に負担をかけない食事形態を心がけます。 -
温熱療法
痛みが筋肉の緊張に関連している場合、温めることで緊張をほぐすことができます。タオルをお湯で濡らして軽く絞り、顎に当てると効果的です。
これらのような応急処置をしてもなかなか症状が消退しない場合は、歯科医院にかかるなどして専門的な診査診断を受けることをおすすめします。
歯科医院や病院での治療法
症状が改善しない場合や強い痛みが続く場合は、早めに歯科または口腔外科を受診することが重要です。
-
薬物療法
炎症や痛みが強い場合、そういった症状を先に抑えるための鎮痛薬や筋弛緩薬が処方される場合があります。 -
スプリント療法
スプリント(マウスピース)で、噛み合わせを安定させることで顎関節の位置も安定させます。それによって顎関節への負担を減少させる治療法です。 -
理学療法
顎の筋肉や関節をストレッチする訓練指導を行います。 - 噛み合わせの治療・矯正治療
上顎と下顎の位置関係や歯の噛み合わせを見直し、改善することで顎への負担を減らすことができます。 -
外科的処置
一通りの治療で効果が得られなかったり、重症の場合や関節円板が変形・癒着・損傷が著しいと診断された場合には、顎関節に対して外科手術が必要となる場合もあります。
まとめ
「あくびの後に顎が痛い」場合、一時的な顎関節症である可能性が高いですが、経過をみたり、適切な対処で症状の消退・改善が見込める場合がほとんどです。顎を安静に保ち、必要に応じて医師の診断を受けることで、痛みの軽減や再発予防が可能です。日常生活で顎への負担を軽減し、健康な顎関節を維持することが重要です。
症状が頻繁に起こる場合は、専門家による診断と治療を受けることをおすすめします。
■ 他の記事を読む■